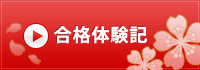現役合格おめでとう!!
2025年 千葉校 合格体験記

芝浦工業大学
建築学部
建築学科/APコース
青木遥香 さん
( 千葉東高等学校 )
2025年 現役合格
建築学部
私は高校1年生から東進に通い3年間東進生でした。1年生時は化粧品開発をしたい気持ちが強く化学系に進学したいと思っていました。しかし、自分は実験よりも物作りをする方が好きであることに気付き、建築学部に進むことを高校2年生で決心し、建築学部に合格することを目標に受験期間勉強を頑張りました。
具体的には、物理と数学が本当に苦手だったので、特にその2教科を強化することに専念しました。数学に関しては、問題の解法をそのまま覚えるのではなく、典型問題の解答をどのように導くかの過程を理解することを意識して勉強しました。
また、物理に関しては、学校で配布されたワークが解けても過去問を解いたら出来ないという状況でした。流石に、勉強方法に欠陥があると思い自分の勉強法を見つめ直した結果、物理現象そのものを理解せず、ある1つの問題に対する解答といったように、1対1対応でしか問題を見ていなかったことが物理が伸びない原因であることが判明しました。この問題は今まで解いた他の問題とどのような共通点があるのだろう、といったように様々な問題を結びつけて関連性を見つけることに注意して問題を解くようにしました。
また、物理現象の基本を理解出来ないことには応用にももちろん繋げられないことを念頭において勉強するべきであることを皆さんに伝えたいです。基本とは公式がわかる、ということではなく現象そのものがどのような原理で起きているのかがわかって初めて基本を理解したと言えると私は思います。このように、基本を追求したり、自分に合った問題集を見つけたりすることで志望校合格を手に入れることが出来たのだと思います。
共テを失敗して言えることは、成績が伸びる機会は急に来るけど、その機会が入試までに間に合うことは難しいということです。だから、皆さんには早いうちから自分に合った勉強法や今やっている勉強法が本当に正しいのかを吟味して欲しいです。これらのことを成し遂げることは本当に難しいと思いますが、諦めずに頑張ってください。応援しています。
具体的には、物理と数学が本当に苦手だったので、特にその2教科を強化することに専念しました。数学に関しては、問題の解法をそのまま覚えるのではなく、典型問題の解答をどのように導くかの過程を理解することを意識して勉強しました。
また、物理に関しては、学校で配布されたワークが解けても過去問を解いたら出来ないという状況でした。流石に、勉強方法に欠陥があると思い自分の勉強法を見つめ直した結果、物理現象そのものを理解せず、ある1つの問題に対する解答といったように、1対1対応でしか問題を見ていなかったことが物理が伸びない原因であることが判明しました。この問題は今まで解いた他の問題とどのような共通点があるのだろう、といったように様々な問題を結びつけて関連性を見つけることに注意して問題を解くようにしました。
また、物理現象の基本を理解出来ないことには応用にももちろん繋げられないことを念頭において勉強するべきであることを皆さんに伝えたいです。基本とは公式がわかる、ということではなく現象そのものがどのような原理で起きているのかがわかって初めて基本を理解したと言えると私は思います。このように、基本を追求したり、自分に合った問題集を見つけたりすることで志望校合格を手に入れることが出来たのだと思います。
共テを失敗して言えることは、成績が伸びる機会は急に来るけど、その機会が入試までに間に合うことは難しいということです。だから、皆さんには早いうちから自分に合った勉強法や今やっている勉強法が本当に正しいのかを吟味して欲しいです。これらのことを成し遂げることは本当に難しいと思いますが、諦めずに頑張ってください。応援しています。

信州大学
人文学部
人文学科
森下文賀 さん
( 千葉市立千葉高等学校 )
2025年 現役合格
人文学部
私は家で勉強するのが苦手だったので高1のときに東進に入りました。毎日学校帰りに東進に寄る習慣をつけたことは、受験生になってとても役立ったと思います。東進の担任の先生や担任助手の方と相談して、自分のやりたいこと、自分の得意、不得意教科に合った受験科目の大学を探しました。そして、信州大学に志望校を決定したことで、勉強する目的意識がはっきりしてモチベーションを保つことができました。
私は長期的な計画を立てるのが苦手なので、1日のうちにやるべき事を決めるようにしていました。その日にやるべきことをはっきりさせると、何を勉強するか考える必要がなくなるので、時間を無駄にせず勉強できたと思います。また、高速マスター基礎力養成講座を毎日やる事を心掛けました。共通テスト対応英単語1800を1日1周し、簡単な単語も忘れないように気をつけました。共通テストも国公立2次も文法の問題は無かったので、単語を全力でやったことは入試全体で役立ったと思います。東進の模試ではE判定以外出したことはありませんでしたが、合格のために必要な勉強を見極め自分に合った勉強を続けていけばちゃんと結果は付いてくると思います。応援しています。
私は長期的な計画を立てるのが苦手なので、1日のうちにやるべき事を決めるようにしていました。その日にやるべきことをはっきりさせると、何を勉強するか考える必要がなくなるので、時間を無駄にせず勉強できたと思います。また、高速マスター基礎力養成講座を毎日やる事を心掛けました。共通テスト対応英単語1800を1日1周し、簡単な単語も忘れないように気をつけました。共通テストも国公立2次も文法の問題は無かったので、単語を全力でやったことは入試全体で役立ったと思います。東進の模試ではE判定以外出したことはありませんでしたが、合格のために必要な勉強を見極め自分に合った勉強を続けていけばちゃんと結果は付いてくると思います。応援しています。

東洋大学
経済学部/第1部
国際経済学科
野中ゆい さん
( 千葉敬愛高等学校 )
2025年 現役合格
経済学部/第1部
私は高校3年生の3月頃入学しました。私の高校自体推薦入試が多く、周りが年内で進路が決まっていく中、1人で勉強するのはすごく苦痛だったし、みんなからの遊びの誘いを断るのも辛かったです。正直受験を辞めたいと思うことが何度もありました。しかし、東進の担任助手の方たちが本気で私に向き合ってくれて、私も本気で頑張ろうと思えたし、担任助手の方のためにも絶対頑張ろうと思いました。
受験が終わった今考えてみたら、失ったものはなかったとは言えないけど、それ以上に得たものが沢山あります。それは、勉強に関してはもちろん、周りが遊んでる中一般受験で耐え抜いた精神力や、自分の性格を改めて知っていい所も悪い所も知ることが出来ました。その中でも特に達成感を味わえたのが私にとって心に残っています。これまでの人生の中で何か一つの目標に向かって本気で努力するという経験をしたことがありませんでした。
大学受験という初めての大きな目標が与えられて、それに向かって毎日を過ごしていき、それを達成した時の感情はこれから経験できないほどのものでした。これは自分にとってのこれからの自信にも繋がるし、一生の財産になると思います。また、これは受験を経験していなければ絶対に得ることができないものだと思います。一般受験を経験して本当に良かったです。そして、この受験期間に得たものを絶対無駄にしないように大学生活を送ろうと思います。
受験が終わった今考えてみたら、失ったものはなかったとは言えないけど、それ以上に得たものが沢山あります。それは、勉強に関してはもちろん、周りが遊んでる中一般受験で耐え抜いた精神力や、自分の性格を改めて知っていい所も悪い所も知ることが出来ました。その中でも特に達成感を味わえたのが私にとって心に残っています。これまでの人生の中で何か一つの目標に向かって本気で努力するという経験をしたことがありませんでした。
大学受験という初めての大きな目標が与えられて、それに向かって毎日を過ごしていき、それを達成した時の感情はこれから経験できないほどのものでした。これは自分にとってのこれからの自信にも繋がるし、一生の財産になると思います。また、これは受験を経験していなければ絶対に得ることができないものだと思います。一般受験を経験して本当に良かったです。そして、この受験期間に得たものを絶対無駄にしないように大学生活を送ろうと思います。

東洋大学
経済学部/第1部
国際経済学科
野中ゆい さん
( 千葉敬愛高等学校 )
2025年 現役合格
経済学部/第1部
私は高校3年生の3月頃入学しました。私の高校自体推薦入試が多く、周りが年内で進路が決まっていく中、1人で勉強するのはすごく苦痛だったし、みんなからの遊びの誘いを断るのも辛かったです。正直受験を辞めたいと思うことが何度もありました。しかし、東進の担任助手の方たちが本気で私に向き合ってくれて、私も本気で頑張ろうと思えたし、担任助手の方のためにも絶対頑張ろうと思いました。
受験が終わった今考えてみたら、失ったものはなかったとは言えないけど、それ以上に得たものが沢山あります。それは、勉強に関してはもちろん、周りが遊んでる中一般受験で耐え抜いた精神力や、自分の性格を改めて知っていい所も悪い所も知ることが出来ました。その中でも特に達成感を味わえたのが私にとって心に残っています。これまでの人生の中で何か一つの目標に向かって本気で努力するという経験をしたことがありませんでした。
大学受験という初めての大きな目標が与えられて、それに向かって毎日を過ごしていき、それを達成した時の感情はこれから経験できないほどのものでした。これは自分にとってのこれからの自信にも繋がるし、一生の財産になると思います。また、これは受験を経験していなければ絶対に得ることができないものだと思います。一般受験を経験して本当に良かったです。そして、この受験期間に得たものを絶対無駄にしないように大学生活を送ろうと思います。
受験が終わった今考えてみたら、失ったものはなかったとは言えないけど、それ以上に得たものが沢山あります。それは、勉強に関してはもちろん、周りが遊んでる中一般受験で耐え抜いた精神力や、自分の性格を改めて知っていい所も悪い所も知ることが出来ました。その中でも特に達成感を味わえたのが私にとって心に残っています。これまでの人生の中で何か一つの目標に向かって本気で努力するという経験をしたことがありませんでした。
大学受験という初めての大きな目標が与えられて、それに向かって毎日を過ごしていき、それを達成した時の感情はこれから経験できないほどのものでした。これは自分にとってのこれからの自信にも繋がるし、一生の財産になると思います。また、これは受験を経験していなければ絶対に得ることができないものだと思います。一般受験を経験して本当に良かったです。そして、この受験期間に得たものを絶対無駄にしないように大学生活を送ろうと思います。

明治学院大学
心理学部
心理学科
森本里咲 さん
( 八千代松陰高等学校 )
2025年 現役合格
心理学部
私は高校2年生の12月に東進に通い始めました。最初は大学受験に対してあまり熱意が無く勉強は単語帳と受講だけで他はほとんどしていませんでした。しかし、夏に共通テストの過去問をたくさん演習して、基礎が抜けていることに気がつきました。そのため、世界史では通史を、古文では文法・助動詞の意味など土台の部分を夏が終わるまでに固めました。そのおかげで、その後の問題演習を苦なくたくさん進めることができました。東進の学習方針では過去問を夏に始めるので早い段階で自分の弱点に気づくことができてよかったと実感しています。
私は世界史の勉強方法が分からずあまり手がつけられずにいたのですが、加藤先生のスタンダード世界史探求の授業は分かりやすく、覚え方やよく出る分野も知ることができるので世界史が苦手な人におすすめです。受験を終えて言えることは、とにかく基礎が大事ということです。例えば英語で言うと単語がまず分からないと文章どころか文法問題ですら不利になってしまいます。私立文系は暗記が勝負なので隙間時間に単語を覚えるだけでも大きな一歩です。その積み重ねを大切に最後まで頑張ってください。応援してます。
私は世界史の勉強方法が分からずあまり手がつけられずにいたのですが、加藤先生のスタンダード世界史探求の授業は分かりやすく、覚え方やよく出る分野も知ることができるので世界史が苦手な人におすすめです。受験を終えて言えることは、とにかく基礎が大事ということです。例えば英語で言うと単語がまず分からないと文章どころか文法問題ですら不利になってしまいます。私立文系は暗記が勝負なので隙間時間に単語を覚えるだけでも大きな一歩です。その積み重ねを大切に最後まで頑張ってください。応援してます。